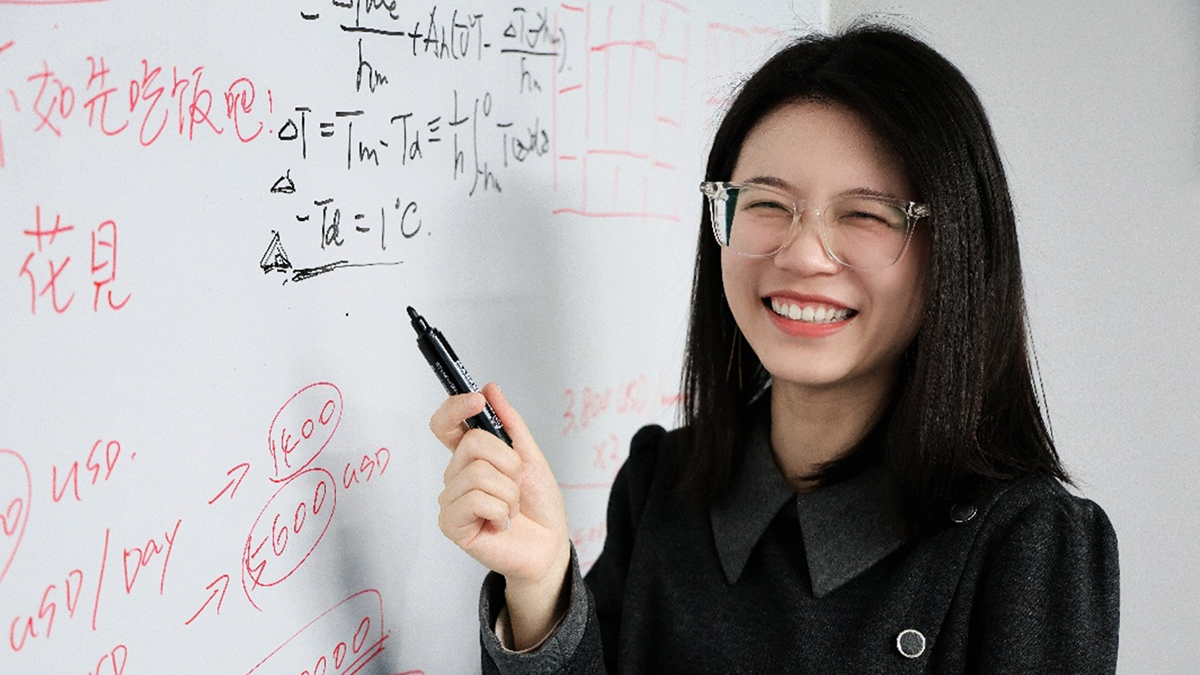コンテンツ
最先端に触れる
2025.11.13
海がもつ記憶:大西洋が太平洋にどう影響を与えるのかを探索する海洋学者の歩み
太平洋はどのようにして大西洋からのシグナルを「記憶」し、数年後にそれに応答できるのでしょうか?
この魅力的な問いは、海洋物理学者のBaolan Wu准教授の最近の研究の中心にあるものです。彼女の研究は、地球上の二大海洋変動パターン間に存在するつながりを明らかにすることです。本インタビューでは、Wu准教授が海洋科学の道へ進んだ経緯と、最近の論文「大西洋と太平洋の数十年規模変動を結ぶ亜熱帯モード水の再出現メモリー」で得られた成果について語っていただきます。
―どのような経緯で海洋物理学者になったのですか?
私は中国の沿岸都市・青島で育ちました。子ども時代に海は最大の喜びのひとつでした。時間とともに海との静かだが、しっかりしたつながりを育みました。それはとても個人的に深くて、心の拠り所となるものでした。この海への親しみから、学部で海洋科学を専攻し、修士では海洋物理学を学ぶことに決めました。他の多くの学生と同じように修士の後も進学するかどうか悩みましたが、転機は修士2年目に訪れました。私は太平洋での研究航海に参加し、船室から甲板に出たとき、どこまでも広がる深い青色の海を目にしました。その光景は息をのむほど美しく、胸を打たれました。その瞬間、私は心に誓いました――この美しい青い海を体験し、理解し、守るために、自分にできるすべてを尽くそうと。この体験が私に明確な目的意識を与え、博士課程に進み、海洋科学に自分の全てを捧げる決意を後押ししてくれました。
―とても素晴らしい機会だったのですね。修士課程ではどのような研究をされたのですか?
研究テーマとしては、南シナ海に焦点を当てるか、あるいは黒潮(日本の太平洋沿岸を北上する大規模な暖流の西岸境界流)を選ぶかの二択でした。私は昔から外洋に魅力を感じていたので、黒潮の研究を選びました。研究はまず、黒潮や親潮続流といった水塊同士の境界、海洋境界前線の調査から始まりました。親潮は亜寒帯から南下する冷たく栄養豊富な海流です。博士課程やポスドク研究に進むにつれ、研究対象はこれらの前線の南に広がる海洋混合層、さらに北太平洋亜熱帯モード水へと広がっていきました。段階を追って、研究は海洋域規模の相互作用や外洋と縁辺海の相互関係を探る方向に向かいました。振り返れば、それは一歩ずつ積み重ねた着実な道であり、各段階が前の研究を基盤にして、統合的で体系的な成果を形作ってきたのだと感じます。

―混合層やモード水とは、具体的に何なのでしょうか?
混合層とは、海の表層部にある一定の深さをもつ層で、風や波、表層流によって水がかき混ぜられ、温度や塩分が比較的一様になっている層です。大気と最も直接的にやりとりをする海の層なので、天気や気候、海洋生態系に重要な役割を果たしています。混合層の下には、特定の地域や季節に形成される「モード水」と呼ばれる特別な種類の水塊が形成されています。モード水は、温度や密度がほぼ均一な厚い水の層で、冬に冷たく密度の高い水が表層直下に沈み込むことで生じます。モード水は熱やその他の性質を数年間保持することができ、長期的なスケールで海洋循環や大気との熱交換に影響を及ぼします。
―最近の研究では、海についてどのようなことを理解しようとしたのですか?
海の興味深い特徴のひとつは、熱を長期間にわたって保持できることです。時には数年間も保持されるのに対し、大気はそれに比べてはるかに早く反応し、長期的に熱をシグナルとして保持することはできません。こうした「過去の気候シグナル(例:温度異常)」を保持する能力が、いわゆる「海洋の記憶」です。私たちの研究の目的は、長期的な海洋温度変動の2つの主要なパターン――大西洋数十年振動(AMO)と太平洋十年規模振動(PDO)――がどのようにつながっているのかを理解することでした。当時の科学者たちは、大西洋の変動(AMO)の後に、約12年遅れて太平洋でも同様の変化(PDO)が現れることに気づいていました。私たちは、この遅れがなぜ生じるのか、そして大西洋が太平洋にこれほど長期的なスケールで影響を及ぼす物理的なプロセスは何なのかを解明したいと考えました。つまり、記憶と時間を介して、遠く離れた2つの海洋域を結びつける海洋メカニズムを明らかにすることが目標でした。
―その遅れを引き起こしている原因を突き止められたのですか?
はい、突き止めました。私たちは、太平洋の「亜熱帯モード水」と呼ばれる特定の水塊が、大西洋からの気候シグナルを蓄え、伝達するうえで重要な役割を果たしていることを発見しました。大西洋の温度変化(AMO)は、地球規模で大気圧のパターンに影響を及ぼします。この変化が「定常ロスビー波」と呼ばれる大規模な大気波動を通じて太平洋にシグナルを送り、それが太平洋西部上空の風のパターンを変化させます。そこはちょうど亜熱帯モード水が形成される場所です。その結果、大西洋によって引き起こされた温度異常がこの水塊に取り込まれるのです。形成された水塊は、「再循環ジャイア (Recirculation gyre)」と呼ばれる海洋内の大規模でゆっくりとした循環流に沿って移動し、最終的に約10年後に黒潮系へと再流入していきます。このメカニズムこそが、大西洋が長い時間差をもって太平洋に影響を与える仕組みを説明するものです。まるで海が気候のメッセージを時間と空間を超えて運び、数年後に届けることで、遠く離れた2つの海洋域の変動を結びつけているかのようです。

―このメカニズムをどのように解明されたのですか?どのようなツールやデータを使ったのですか?
まず、三次元の海洋の水温・塩分のデータセットを解析し、亜熱帯モード水の空間構造をマッピングしました。これにより、どこで形成され、深さによってどのように変化するのかを明らかにしました。もうひとつ重要な手法が「ラグランジュ的粒子追跡」です。これは時間の経過とともに水塊の移動をシミュレーションする方法で、何千もの仮想的な浮遊物を海に放流して、その行方を観察するようなものです。これにより、モード水が太平洋を横断する具体的な経路を追跡できました。私たちが扱ったのは、十年から数十年以上のタイムスケールで異なる2つの海洋域の相互作用だったため、地球規模をカバーし、かつ長期間にわたるデータセットが必要でした。そのため、約80年分の3種類の観測データと、140年前までさかのぼる海洋の再解析データを1種類使用しました。
―観測データとコンピュータモデルの両方を使われたのですね。どちらか一方では不十分なのでしょうか?
観測データは実際に何が起きたのかを示すもので、必要なものですが、すべての気候研究の基盤となります。しかし海は広大で、観測は常にすべての地域を網羅しているわけでも、十分に長い期間に及んでいるわけでもありません。そこでコンピュータモデルの出番になります。長期的なパターンを探り、仮説を検証するために、私たちは地球規模の気候シミュレーションを用いてさらに掘り下げていきました。その中には「ペースメーカー実験」と呼ばれるモデル実験も含まれます。これは特定の地域の海面水温(SST)を観測値に固定し、その影響を広範な気候システムで調べるものです。私たちの場合は、大西洋(つまりAMO)における暖相や寒相を人工的に導入し、太平洋がどのように反応するかを解析しました。これにより因果関係を切り分けて理解することができました。観測データ、長期シミュレーション、そしてペースメーカー実験の結果が一致すると、研究の信頼性が高まり、将来の気候変動を数年、さらには数十年先まで予測できる自信につながります。
―なぜ数十年先の気候変動を予測できることが重要なのですか?
天気予報が一週間先の生活の計画に役立つのと同じように、長期的な海洋・気候予測は海洋環境の健全性や資源の管理に役立ちます。より正確な予測ができれば、漁業、海洋生態系、沿岸計画といった、私たちの生活に直結する分野において、より良い判断が可能になります。現状では、北西太平洋のように大きな気候変動が起こる重要地域において、予測が苦手な海洋モデルが多く存在します。私たちの研究は、そのような変動を引き起こす理論的な背景の理解を深めるものです。長期的な気候変動を駆動する物理メカニズムを特定することで、より信頼できる海洋予測を、次の日のものだけでなく、次の10年に向けても可能にしていけるのです。
―今後、海についてどのようなことを理解したいと考えていますか?
近年、日本の東北沿岸で発生した極端な海洋熱波は、海洋生態系や地域の漁業に深刻な被害をもたらしました。しかし、これらの現象の背景にある仕組みはまだ十分に理解されておらず、次の発生を予測するのは難しいのが現状です。現在、私はスクリプス海洋研究所と共同で、この極端な熱波を引き起こすメカニズムの解明に取り組んでいます。特に注目しているのは、熱帯太平洋や北大西洋から伝わる遠隔的な気候シグナルの役割です。従来の研究ではあまり重視されてこなかったこれらの遠隔影響が、将来の海洋熱波の予測において重要な鍵を握っている可能性があります。こうした長距離のつながりを解明することが、早期警戒システムの改善につながり、海と、それに依存する人々の暮らしを守る一助となることを目指しています。
インタビュー・文
Nadine Wood(WPI-AIMEC特任准教授(運営)、科学アウトリーチ・国際コーディネーター、東北大学)
リンク
Paper (published on February 14, 2025, in the scientific journal “National Science Review”)